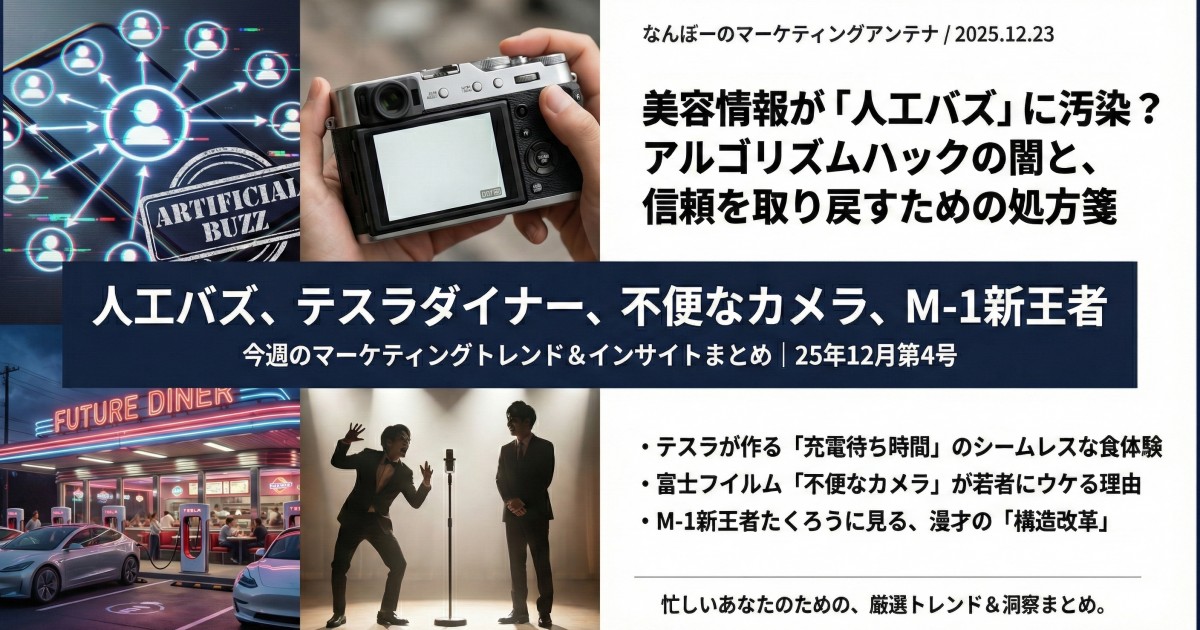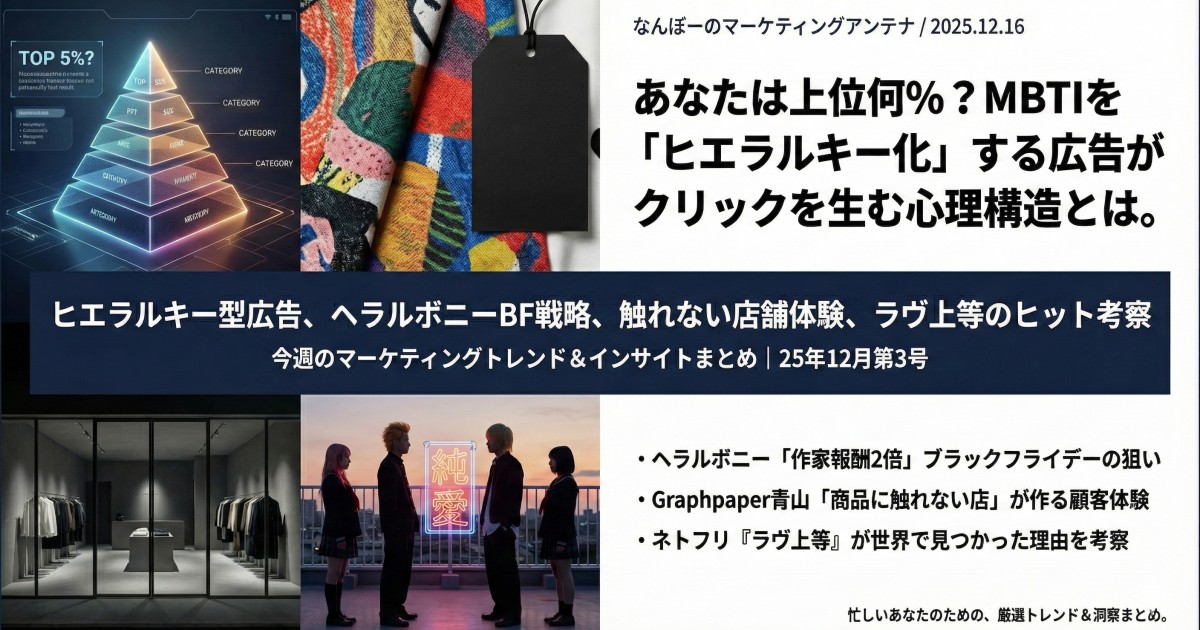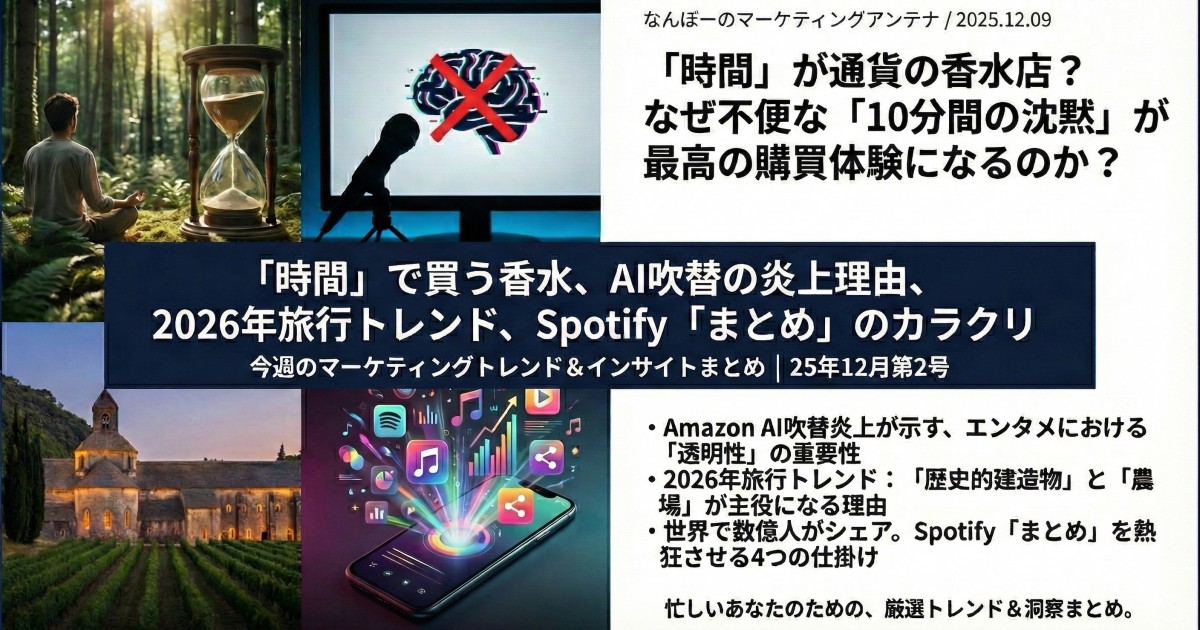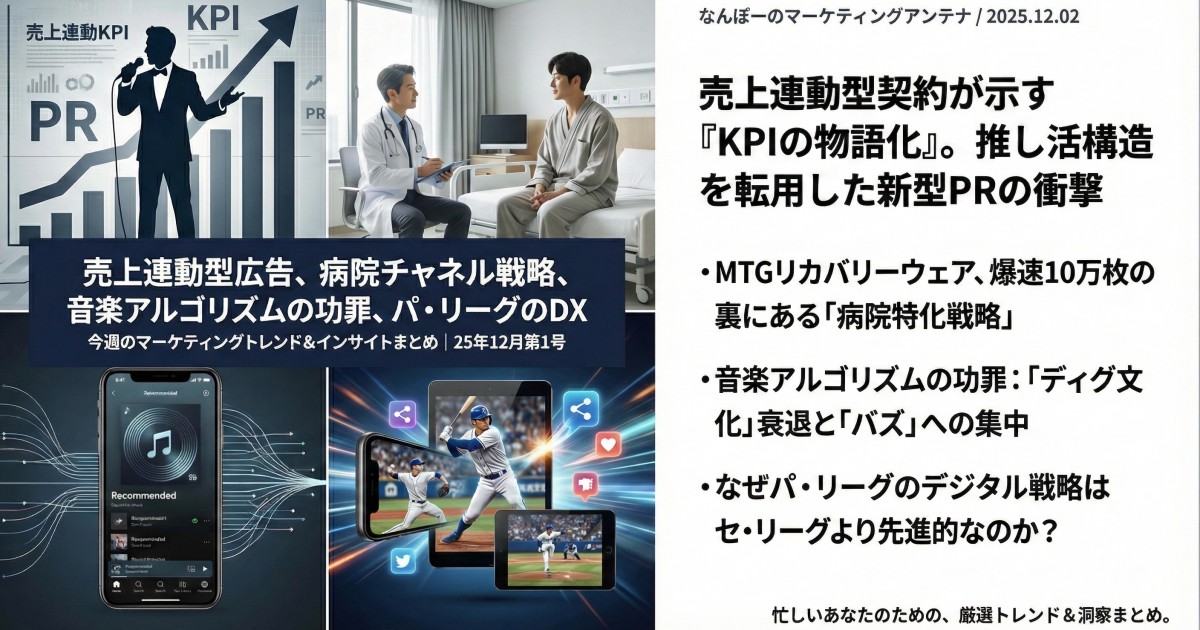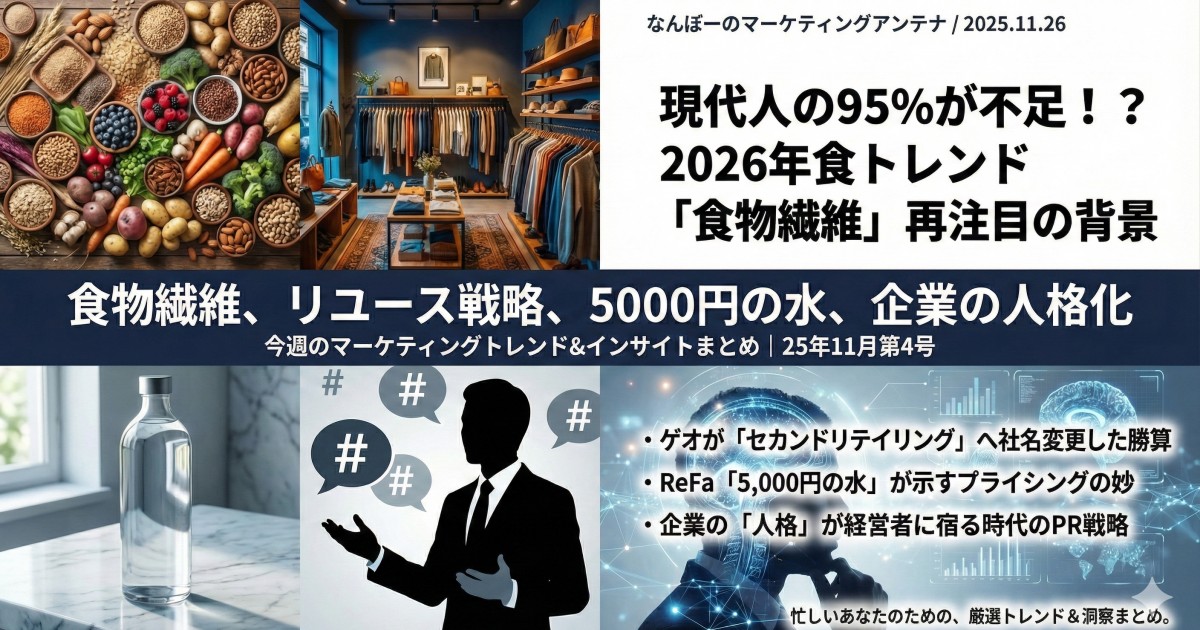Z世代女性の8割が経験する「ぬい活」ぬいぐるみが届ける「やわらかな自己表現」とは? 25年6月第2号
忙しいあなたのためのマーケティング情報サプリメント。週に一度、厳選されたトレンドと洞察をまとめていきます。これを読めば「主要なトレンドをキャッチできる」、そういった想いで届けてまいります。まずはご登録をお願いいたします。
マーケティングトレンドインプット 今週のクイック解説3選
冷たさを「商品哲学」に昇華させるスーパードライの温度ブランディング
「辛口」で知られている日本で最も売れているビール、アサヒスーパードライが、新しいブランディングに挑戦している。そのキーが「温度」。飲んだことがある人なら分かる通り、辛口ピルスナーなスーパードライは温度が低い方がその価値を感じられる。この「スーパードライの商品価値を最高に感じられる状態」のキーとなる温度にあらゆる顧客接点でこだわるというアプローチをしているのだ。
料飲店で低い温度を実現するお店を認定、さらに低い温度で変わるパッケージ、そして冷たさを感じられる特性タンブラーの配布。料飲店、量販店、家、全ての接点で温度に気を付けて顧客に飲んでもらい、そして冷たさの価値に気づいてもらう。この体験を再現させるために「気づいてもらう」仕組みを様々な場所でしかけているというかたち。
辛さだけでなく「冷たさ」という温度を商品に取り込み、最高の状態で再現すれば美味しい、と体験までブランディングに混ぜていくチャレンジ。非常に本質的で素晴らしい取り組みだと感じます。
「やわらか自己表現」としてのぬいぐるみ Z世代に広がる「ぬい活」
SHIBUYA 109 lab.の調査によれば、15〜24歳女性の8割超が“ぬい活”を経験しているとのこと。ぬい活とは、自分の推しの人物や、お気に入りのキャラクターをぬいぐるみとしてバッグにつけるなどして持ち歩くという行動のこと。中国POPMARTで大人気のラブブやちいかわを付けるなど、ぬいぐるみそのものがチャームになっている傾向の中で、更に推しを要素がミックスされている現象です。
ぬいぐるみはZ世代女子にとって「新しい自己表現メディア」になっているということだと思っていて、この非常に目立つ存在が他者とのコミュニケーションを生んだり、他者に対する自分の紹介として機能、あるいは推しへの愛の表明にもなっているということなのだろう。「ぬい」は持ち歩ける分身であり、ミニチュア的な役割もあるかもしれないですよね。「ぬい」さえいればいつものカフェも推し活写真を撮る場に変化する。
もう1点、ぬいぐるみは「直接的じゃない」価値があるんじゃないか。写真やロゴなどほどより露骨でなく、推し活をマイルドにする「やわらか」な役目もある気がする。そもそもの見た目もマイルド。K-POPではアイドルをキャラクター化する試み(StraykidsのSKIZOOなど)も拡大しているが、そうした文化との連動もありそうです。
「時間を価値に転換する」キリン人生を共に生きるウィスキーの巧みなプロダクト設計
キリンが公開したMakuakeのプロジェクト「人生を共に生きるウィスキー」は2億円以上という驚異的な金額でサクセス。この商品は誕生年原酒を購入すると3年・7年・10年・13年・16年でサンプルが届き、20年目に最終ボトルが届くという20年にわたる長期の商品。価格は驚きの11万円。
単純に待つだけでなく、数年ごとに中間サンプルでウィスキーのエイジングという価値を実感するだけでなく、継続的なブランド接触を実現しているのが特徴。よく「誕生日年のワインやウィスキーをプレゼントする」という手法があるが、これをゼロ年から価値化するというのはありそうでなかった非常にロマンがあって素敵な商品設計だなと感じます。
ウィスキーは素早く作ることはどうしても難しいプロダクト。だからこそそのかかる時間を価値にして、成人式や結婚記念日、あるいは会社の周年記念など、ライフイベントと連動させる設計にしているからこそ、誰にでも価値を感じやすく、これだけの金額が集まるクラウドファンディングになったんだろうなと。味覚だけでは測れない「時間」をある種商品化しているような印象で、従来型とは異なるブランド価値を生み出した素晴らしい事例ですね。
源泉かけ流し!今週のマーケティング関連トピックス(今週は25個ご紹介!)
BCG消費者心理調査--価格設定の高度化を見据えて
BCGが出している「価格の許容度」に関するレポート。
ダイナミックプライシングの受容性がわかりやすいです。
-
原材料や人件費高騰での値上げは理解されやすい
-
商品自体の変更は納得する理由が必要
-
同一商品でも価格が異なることは当たり前に
-
「学割」「シニア割」は受け入れられやすい
1日3食は、もはや当たり前ではない?時代を象徴する「0.5食」
1食未満の「0.5食」が増えている、という分析。
実は1日3食食べている人はわずか7%しかいないらしい。
在宅が増えていることも踏まえ、自由なタイミングで簡単なものを適量食べている、人が増加。
食事の時間や手間を十分にかけずに食べる、ちょっとした食べ物や飲み物が「0.5食」ということ。
この記事は無料で続きを読めます
- 海外現地調査レポート:たった1年で超人気になったお土産特化型新ブランド「newmix coffee」
- 明日から効く!マーケティング/ブランディング関連書籍レビュー
- 1年後に効くかも?あなたにおススメなインプット
- 今週の1曲
- 最後に!
すでに登録された方はこちら